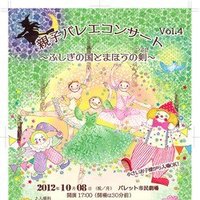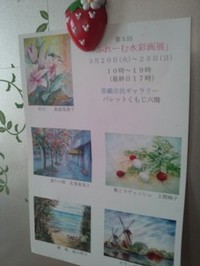2007年01月30日
ムーチー
沖縄の餅は、もともと糯米(もちごめ)を水を加えつつ石臼で碾(ひ)くか、水に浸しておいた糯米(もちごめ)を搗(つ)くかした後、蒸しあげたものが中心だが、近年は糯米粉(もちごめこ)を水で練って作るのが普通。そんな餅の中でも、旧暦十二月八日に作るのが鬼餅(ムーチー)。練った糯米粉(もちごめこ)を平たくのばし、細長い長方形をつくってサンニン(月桃(ゲットウ))やクバ(蒲葵(ビロウ))の葉で包んで蒸す。特に、香りのよいサンニンで包んだものは人気があり、今では街の菓子屋で一年中買える。黒砂糖味のものもある。
鬼餅(むーちー)には厄払いの意味があり、仏壇、かまど、神棚などに供え、家族一同、特に子供の健康を願う。
その昔、首里(しゅり)の金城(かなぐしく)に兄と妹が住んでいたが、兄が大里(おおざと)に移ってから人を喰う(くう)鬼となった。妹は兄が首里を訪ねて来た時、それを退治するため鉄餅とふつうの餅を作って自分はふつうのものを食べ、兄には鉄の方を渡した。鉄餅を食べられず困っている兄の前にわざと着物の裾を開いた妹がすわると、下の口が兄の目に入った。それは何かと問う兄に、『上の口は餅、下の口は鬼を食べるのよ』と答えると、兄は驚いて崖から転げ落ち死んでしまった、というのが有名な鬼餅(むーちー)由来。鬼(厄)を払うありがたい餅なのだ。「オキナワなんでも事典」より
 すげーリアルな話です
すげーリアルな話です
鬼餅(むーちー)には厄払いの意味があり、仏壇、かまど、神棚などに供え、家族一同、特に子供の健康を願う。
その昔、首里(しゅり)の金城(かなぐしく)に兄と妹が住んでいたが、兄が大里(おおざと)に移ってから人を喰う(くう)鬼となった。妹は兄が首里を訪ねて来た時、それを退治するため鉄餅とふつうの餅を作って自分はふつうのものを食べ、兄には鉄の方を渡した。鉄餅を食べられず困っている兄の前にわざと着物の裾を開いた妹がすわると、下の口が兄の目に入った。それは何かと問う兄に、『上の口は餅、下の口は鬼を食べるのよ』と答えると、兄は驚いて崖から転げ落ち死んでしまった、というのが有名な鬼餅(むーちー)由来。鬼(厄)を払うありがたい餅なのだ。「オキナワなんでも事典」より
 すげーリアルな話です
すげーリアルな話ですPosted by kyoko.k at 11:52
│family
この記事へのコメント
うちも一緒だよ~♪
実家も初の内孫でムーチーを200個作ったからそのおふそわけと、旦那の実家も毎年作るから、家にはまだまだムーチーがたっぷり!!
チビラスちゃん、風邪でも引いた?
実家も初の内孫でムーチーを200個作ったからそのおふそわけと、旦那の実家も毎年作るから、家にはまだまだムーチーがたっぷり!!
チビラスちゃん、風邪でも引いた?
Posted by marimama at 2007年01月30日 14:59
すごーい。
うちはだんなの実家が新で行事をする地域に住んでいるので、ムーチーも新ですみました。
でも、いつも保育園でつくるせいか、いえではつくらないのでらくかな。
marimamaの200個というのもすごいですね。
うちはだんなの実家が新で行事をする地域に住んでいるので、ムーチーも新ですみました。
でも、いつも保育園でつくるせいか、いえではつくらないのでらくかな。
marimamaの200個というのもすごいですね。
Posted by ちばおはむ at 2007年01月30日 23:30